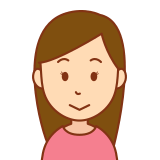
・共働き夫婦で住宅ローンを組むにはどの方法がいいか悩んでいる。
・借り換えを機に前回と違う組み方も検討してみたい。
理想の物件を購入するために、収入合算を検討しているご家庭もあると思います。
収入合算をするメリットは、単独で住宅ローンを組むよりも借入可能額を増やせる点です。一方、デメリットとしては、借入金額が大きくなることで、返済が厳しくなるリスクがあります。
また、収入合算と似たような方法に、夫婦が1人ずつローンを組む「ペアローン」もあります。
住宅ローンの組み方によって、住宅ローン控除の適用や団信の加入にも関係するため、しっかり比較検討をすることをおすすめします。
この記事では、
- 住宅ローンの組み方の種類とおすすめ
- ローン組み方と団体生命保険の仕組み
- 組み方のメリット・デメリット
について紹介しています。
住宅ローンの組み方の参考にしていただけると幸いです。
住宅ローンの組み方の種類とおすすめ
| 種類 | おすすめ |
|---|---|
| 【収入合算】 連帯債務型 | 夫婦ともに年収103万円以上(住宅ローン控除が利用できる) 片方の収入だけでは借入希望額に満たないとき |
| 【収入合算】 連帯保証型 | 片方の収入だけでは借入希望額に満たないとき |
| ペアローン | 夫婦ともに正社員で安定した収入がある場合 |
| 単独で組む | 単独でも、希望金額を借りられる場合 または、片方が専業主婦(夫)の場合 |
組み方の比較表
※3,000万円ローンを組む場合
| 種類 | 収入合算 | ペアローン | 単独債務 | ||||
| 連帯債務型 | 連帯保証型 | ||||||
| 債務者 👨 | 債務者 👩 | 債務者 👨 | 連帯保証人 👩 | 債務者 👨 | 債務者 👩 | 債務者 👨 | |
| 契約数(借入金額例) | 1 (3000万円) | 1 (3000万円) | 1 (1500万円) | 1 (1500万円) | 1 (3000万円) | ||
| 住宅ローン控除 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 団体信用生命保険 | ○ | △ 夫婦連生団信 に加入の場合 は対象 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 所有者名義 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
住宅ローン控除は年収2000万円以下かつ入居開始から10年間(入居時期が2019年10月以降の新築物件の場合は13年間)適用されます。
詳しくはこちら>>借り換えたら住宅ローン控除はどうなる?
ローン組み方と団体生命保険の仕組み
| 組み方 | 団体信用生命保険 |
|---|---|
| 連帯債務 (夫が主債務者、 妻が連帯債務者の場合) | 夫:死亡・高度障害等時は返済免除される 妻:死亡時は返済免除されない(夫婦連生団信を除く) |
| 連帯保証 (夫が債務者、 妻が連帯保証人の場合) | 夫:死亡・高度障害等時は返済免除される 妻:死亡・高度障害等時は返済免除されない |
| ペアローン | 死亡や高度障害等になった側の住宅ローンは返済免除されるが、 もう一方のローンは返済免除されない |
| 単独で組む (夫債務者の場合) | 夫:死亡・高度障害等時は返済免除される 妻:死亡・高度障害等時は返済免除されない |
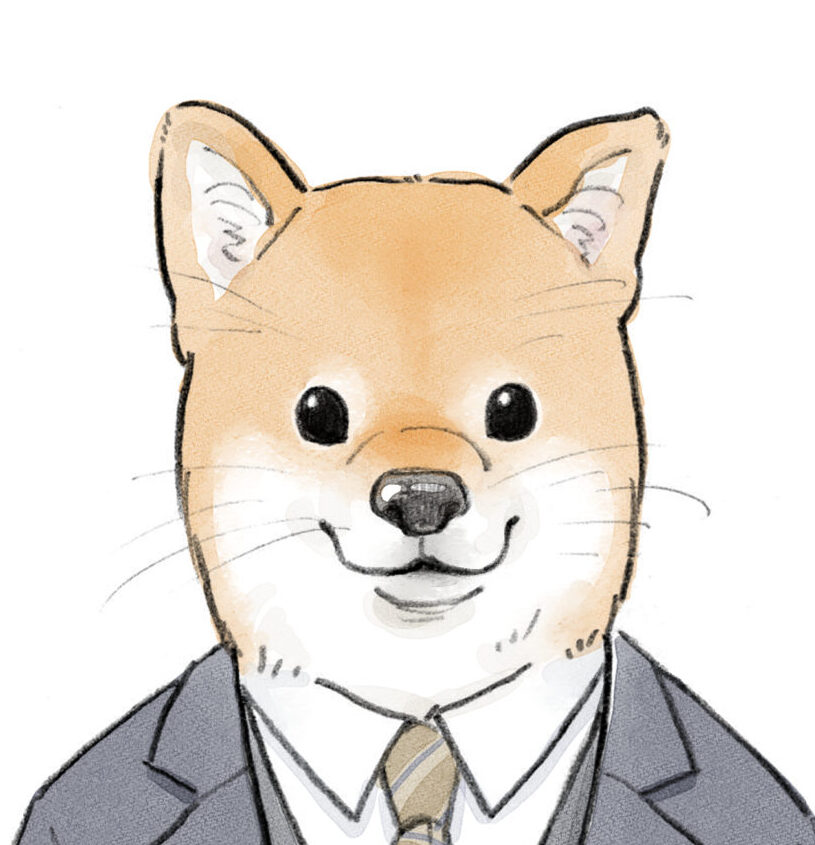
ペアローンはそれぞれ契約を組んでいる形なので、死亡や高度障害等になった側の住宅ローンは完済の対象となりますが、もう一方のローンは免除されません☜落とし穴に注意
【収入合算】連帯債務型のメリット・デメリット
「連帯債務型」は住宅ローンを2人とも返済する義務があるのに対し、「連帯保証型」は、債務者が払えなくなった時に、連帯保証人に肩代わりの義務が生じます。
連帯債務型で組む場合、夫婦のどちらか1人が主債務者、もう1人が連帯債務者となり、1つの住宅ローンを夫婦で契約・署名します。
また連帯債務者も主債務者と同じ債務を負うことになります。
一般的に連帯債務とは、片方の収入では借入希望額に満たないときに、配偶者の収入を合算させ希望額を借りるために選ぶ方法です。
金融機関によってはパートでも連帯債務者になれる場合があります。
- 住宅ローン控除(減税)の適用を二人とも受けられる
- 諸費用の負担が1契約分で済む
- フラット35を除き、基本的に連帯債務者は団体信用生命保険に加入できない
- 完済まで共働きが前提となる→パートナーが働けなくなれば月々の返済が厳しくなる
- 離婚した場合、共有名義のため手続きが煩雑になる
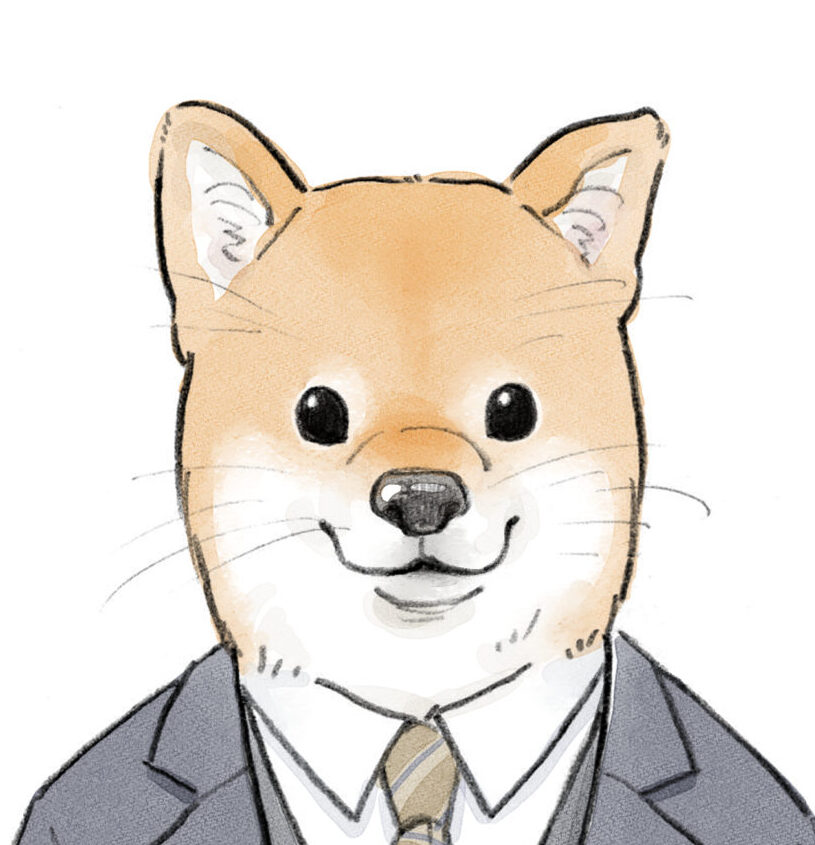
例えば3,000万の家を購入し、住宅ローンを夫2,000万、妻1,000万で借りた場合、
持ち分比率をローンの負担比率と同じ夫2/3、妻1/3とした場合は贈与税かかりません。
ところが持ち分比率を夫1/2妻1/2とすると、夫から妻への贈与したとみなされ、税金が発生します。
【収入合算】連帯保証型のメリット・デメリット
連帯保証型の住宅ローンは基本的に少ないですが、
片方の収入では借入希望額に満たない場合、配偶者の収入(パートの収入等)を合算して、希望金額を借りる方法です。
- 物件は単独所有のため、売却時の手続きがしやすい
- 連帯保証人が仕事を辞めやすい
- 主債務者が支払えなくなれば、連帯保証人が無職でも、連帯保証人に返済の義務が発生する
- 離婚などで連帯保証人を外したくても簡単に外すことができない
- 連帯保証人は団体信用生命保険に加入できない
ペアローンのメリット・デメリット
ペアローンとは、夫と妻がそれぞれ別に住宅ローンを1つずつ、計2つ契約する方法です。
また夫と妻はお互いの連帯保証人となります。
一般的に夫婦ともに正社員で安定した収入がある場合に選ぶ方法です。
- 住宅ローン控除(減税)の適用を二人とも受けられる
※住宅ローン控除額の適用は所得税と住民税の範囲内。
【住宅ローン控除額】>【所得税+住民税】となり、住宅ローン控除額を全額使いきれない場合は、単独債務より、ペアローンのほうが減税効果が高くなる。
- 夫婦ともに団信に加入できる
- 2契約分、手数料がかかる
- 完済まで共働きが前提となる→パートナーが働けなくなれば月々の返済が厳しくなる
- 離婚などで売却したい場合、共有名義のため手続きが煩雑になる
- 死亡や高度障害等になった側の住宅ローンは完済の対象となりますが、もう一方のローンは免除されない
単独債務のメリット・デメリット
夫、妻どちらか収入が安定している方が単独で住宅ローンを組む方法です。例えば、夫が正社員で収入が安定しており希望額を借りられる場合はひとりで組むことができます。
- ひとりで返済可能な借入範囲内である
- 物件は単独所有のため、売却時の手続きがしやすい
- 債務者が死亡・高度障害等になった際に、ローンが完済なる
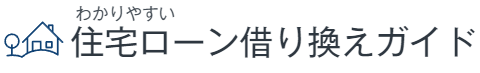
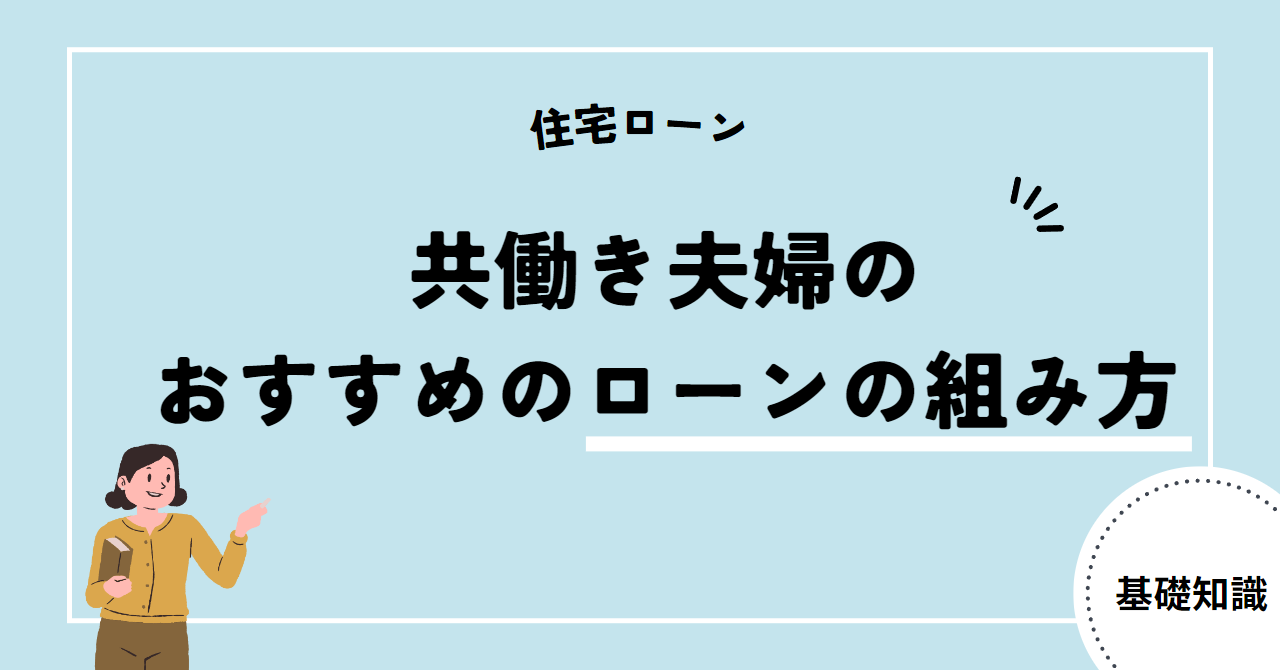
コメント